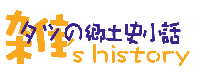土俵上の哀愁-ある「広瀬川惣吉」考
柴田町出身でただ一人、幕内まで昇った力士 広瀬川惣吉 を中心にした展示が、しばたの郷土館でできないかと思うようになったのは、白石市の古い旅館が所蔵していた明治から昭和30年代にわたる大量の番付の整理を手伝う機会があったことによる。
船岡の大沼端に生まれた広瀬川は、本名を及川惣吉といい、先祖をさかのぼれば、船岡邑主柴田氏の下級家臣にたどりつく。生家は昭和12年、第一海軍火薬廠建設にともない立ち退きを余儀なくされ、一家は常磐地方に移り、惣吉は小結桂川質郎にスカウトされて角界入りし、伊勢ヶ濱部屋の門をたたいた。と、書くのが力士略歴表記の常套句であるが、広瀬川の場合、「門をたたく」という積極性があたっていたか、疑問がのこる。立ち退きを余儀なくされ、否応無しに己の立つ瀬を自ら探さざるを得ない状況にあったときに、桂川の巧みな誘いがあった、ということではなかったか。 当時、桂川という頭脳巧者を得て伊勢ヶ濱部屋は勢力拡大をはかろうとしており、槻木からも角界入りした人がいる。力士修業の厳しさが話題になるとき、旬日を経ず逃げかえったという、この人が引合いに出されるのはいささか気の毒の感がある。同じ桂川がスカウトした広瀬川は桂川同様上背はなかったが、相撲巧者振りを受け継いだ。 いずれも大正10年前後に生まれた、私には両親と同じ世代に属する。 昭和27年、前頭三枚目が最高位で、船岡に巡業で来たのはこのころであった。一緒に来た同年齢の照国は横綱だった。美男をうたわれた吉葉山はまだ横綱になっていなかった。 34年40歳で引退したときは髷に白髪がまじる十両十九枚目であった。幕内通算勝率は4割5分に少し及ばなかった。この勝率は前頭の力士としては平均的な数字である。引退後は千葉県で養鶏業を営んだが、成功はしなかったもののようである。54年、60歳で亡くなった。 コレクターのネットワークというのであろうか、その繋がりによって、広瀬川の資料はそれほど多くはなかったが、県出身力士の資料をあわせると狭い展示室をはみ出して展示するまでになった。 そのなかで大きな収穫は広瀬川の遺児片岡浩氏が、関取が撮影したであろう八百点あまりのネガを所蔵しておられ、これを一括して借りることができたことである。 子細に点検するまでもなく、撮影されたのは昭和30年前後であろうことは見当がついた。フォトヴィウアーを使ってテレビに映しだされる関取の遺作を見ているうちに、私は不思議な感情に襲われていた。 ネガにあったのは、私がこれまで見たことのない風景であった。多くは関取が巡業先で撮影したものであり、宮城県内で撮影されたものはなかった。見たことのない風景ではあったが、なつかしい風景であった。 次々に映しだされる映像のなかに、口を開いて力士を見上げる少年たちがいる。その、会ったこともない、見たこともない少年たちは私自身だった。心に掛かることなど何もない、明るい未来に浮き立つわけもなく、閉塞された未来が待っていることなど考えることもなく在った、それでいて何か心細く、不安げな小学生の私。その私がテレビの受像機のなかからこちらを、私をみつめている。 私たちは借用したネガのなかから、約80枚をプリントし、そのなかから半数ほどを選んで展示した。 ポスターに使用する写真をめぐって若いスタッフたちと衝突した。私は共同通信社発行の『大相撲力士名鑑』で使用されている、アイドル系の若々しい広瀬川の写真を使いたかった。スタッフたちは片岡さん所蔵のネガからおこした、腕組みする中年力士の写真を選んだ。私は口を極めてその写真を貶した。スタッフたちは無言で私の言葉をやり過ごし、言葉を使いはたし私はスタッフたちに従った。 ポスターになった写真を毎日みているうちに、私はいつしかこの中年の力士に、私よりはるかに若くなってしまったこの中年の力士に話しかけるようになっていた。 −土俵は楽しかった? −悔いはない? 遠くを見つめる眼差しの、この力士はもちろんなにも応えはしない。 プリントし展示した写真は、結果として巡業を強く意識したものとなった。その写真を見ていると、私は今回の展示に協力してくれた仙台市荒町の古書店の主人の言葉を思い出す。 毘沙門さんの名で知られる荒町の満福寺の境内では、藩政時代、頻繁に「晴天十日」の興行が開かれている。幕末の横綱秀ノ山雷五郎の供養碑があり、となりには七代目式守伊之助の墓がある。毘沙門さんから南鍛冶町まで足をのばせば谷風梶之助の生家金子家の菩提寺東漸寺があり、供養碑が建っている。 荒町周辺は旧市街地のなかでも寺院が数多く残る地区である。古書店の主人によれば、それらの寺の墓地には、他郷出身の力士の墓もあるという。毘沙門さんでの興行の際には、荒町やその周辺の寺に分宿することになる。顔馴染みになった住職に、彼らは万が一の時の弔いを依頼したという。 「一年を二十日で暮す良い男」。実はその残りは旅から旅の巡業暮し、根無し草の寄る辺なき己が身の哀れを集く虫の音に感じ、住職相手に来し方の辛さを訴え、行く末の頼りなさを嘆いたものであろうか。 古書店主の言葉を念頭に写真を見ていると、なつかしい風景の彼方に哀感がある。 幌のないトラックやトロッコに乗り込む力士たち、掘り起こされた土砂の山の向こうに見えるやぐら、河原に運びこまれた風呂桶、かたわらで洗濯する若い力士、まわしを取って水浴びをしようとしている力士もいる。 彼らは決して「一年を二十日で暮す」旅から旅の寄る辺なき身の上ではなくなっていたはずである。が、私にはどうしても異郷に眠る力士たちとダブって見えてしまう。強靱な肉体を売り物にする力士たちだからこそ、短くはかない盛りの哀感が、通奏低音のように感じられるのかもしれない。
広瀬川は40歳で引退した。勝ち味が遅く、上位では苦労したという。おそらく彼は「相撲道を極めよう」などと思ったことなど一度もなかったに違いない。スポーツ根性物語とは無縁のところにいた。
180センチと、当時としては大型といわれた広瀬川であったが、その「恵まれた肉体」が、つねに恵まれたものであったか。巨人力士はかつて、格闘家としてより、意に反して巨大な肉体をさらして見せ物となる存在であったという歴史がある。 広瀬川自身、格闘が好きだった様子はない、むしろ、争いごとは嫌いだった。しかし、とにかく厳しい稽古に耐えうるだけの肉体に「恵まれ」ていた。そして、恵まれた肉体ゆえに、意に反して土俵に上がった。いわば、己の「恵まれた肉体」を受け入れたように、望まぬ土俵生活を、格闘家の人生を受け入れた。 陽が昇って目が覚めるように、呼出しに呼び出されて土俵に上がる。相手がぶつかってきたから受けとめる。さて、それからどうしようかと思う。自身が何かを仕掛けるより相手の出方を待つ。勝つこともあれば負けることもある。勝敗は相半ばした。どうしても勝ってやろうなどとは思わなかった。そのような土俵を想像してしまう。 そして、ポスターの写真を見て、 −土俵の上はどうでした? −人生は? |